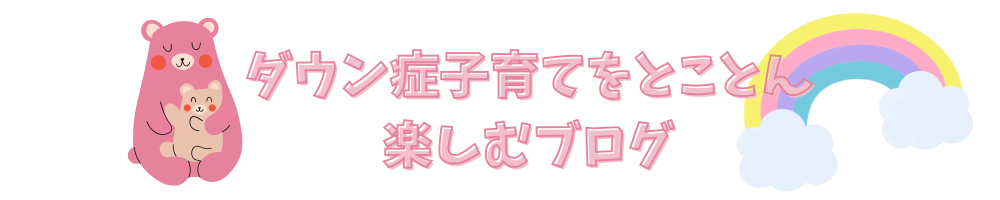こんにちは。ゆうママです。
本日も「脳育」頑張ります!
赤ちゃんがぐっすり眠る姿、本当に愛おしいですよね。
我が家の長男はダウン症をもって生まれてきました。
赤ちゃんの頃はとにかくよく眠る子で、その寝顔に何度も癒されました。
そんな彼の育児で意識したのは、生活リズムを整えること。
夜寝る時間、昼寝、朝起きる時間をなるべく一定にして、リズムを崩さないよう心がけてきました。
イベントがあっても、睡眠リズムを優先する生活。
なぜそこまで睡眠リズムを大切にしているのか?
それは、睡眠が「脳」や「発達」「情緒」など子どもの成長にとって、とても大切な役割を果たしていると学んだから。
睡眠が赤ちゃんや幼児の脳にどんな影響を与えているのかを知ると、自然と生活リズムを整えてあげたくなりますよ。
今回は、睡眠が子どもに与える影響やリズムの整え方について、私の実体験も交えながらお話しします。ぜひ参考にしてみてください!
睡眠の基本と重要性
睡眠は単に体を休めるだけではなく、脳の発達や調整に深く関与しています。以下は睡眠中に起きる代表的な脳の活動です。
【睡眠中に起きる代表的な脳の活動】
- 記憶の定着(情報処理)
一日の間に得た情報や経験が、睡眠中に脳で整理され、長期記憶として保存。
特に幼児期は言語や新しいスキルを学ぶ重要な時期で、睡眠はそのプロセスを助けます。 - 成長ホルモンの分泌
深い眠り(ノンレム睡眠)の間に成長ホルモンが分泌され、体や脳の成長を促します。
これが、赤ちゃんや幼児が特に長時間眠る理由の一つ。 - シナプスの再構築
シナプス(神経細胞の接続)が不要なものを削除し、必要なものを強化。
この「脳の大掃除」が行われることで、効率的な情報伝達が可能に。
子どもと赤ちゃんの睡眠の役割

赤ちゃんや子どもは大人よりも長い時間眠る必要があります。それはなぜでしょうか?
睡眠の不足や質の悪さが脳や行動に及ぼす影響
睡眠が赤ちゃんや子どもに重要な事が分かりましたが、それでは睡眠の不足や質の悪さが脳や行動にどのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。

脳への影響 主な4つ
夜更かしが続くと、翌日に子どもがぐずりやすくなりますよね。
睡眠不足や質の悪い睡眠は、脳の発達や働きに直接的な悪影響が。
十分な睡眠を取らないと、以下のようなリスクが脳に生じると言われています。
(1) 記憶力と学習能力の低下
記憶の整理が不十分に。
睡眠中に脳は情報を整理し、長期記憶に保存。
睡眠不足だとこのプロセスが妨げられ、新しく学んだことを忘れやすくなります。
例: 幼児が新しい単語を覚えられない、学童期の子どもが学校で習った内容を思い出せない。
(2) 集中力の低下
脳の前頭前皮質(思考や意思決定を担う部分)の働きが鈍化。
注意力が散漫になり、学びや遊びに集中できなくなります。
例: 落ち着きがなくなる、指示を聞けなくなる。
(3) 情緒コントロールの乱れ
感情を調整する役割を持つ扁桃体が過剰反応しやすくなるため、ちょっとしたことで怒ったり泣いたり。
例: 幼児がすぐに癇癪を起こす、学童が友達とけんかしやすくなる。
(4) シナプスの適切な再構築が阻害される
脳の神経細胞同士の接続が整理されないため、情報処理能力が低下。
これが続くと発達に遅れが出る可能性が。
行動への影響 主な3つ
脳への悪影響が分かったところで、次は日常生活への影響。
睡眠不足や質の悪さは、日常生活や行動にも具体的な変化をもたらします。
(1) 多動や衝動性の増加
注意欠如・多動症(ADHD)に似た行動を示すことがあります。
過剰に動き回ったり、待つのが苦手になったり。
(2) 社会性の低下
他者との関わりを楽しむ余裕がなくなり、対人関係がぎくしゃくすることがあります。
例: 友達とのトラブルが増える、集団行動に参加しにくくなる。
(3) 疲れやすさとぐずり
体力が回復せず、日中の活動中に疲れを感じやすく。
その結果、ぐずる頻度が増えます。
例: 外出先で突然泣き出す、夕方に極度に不機嫌になる。
長期的な影響 主な3つ

慢性的な睡眠不足が続くと、以下のような長期的リスクが生じます。
(1) 学力や発達への遅れ
知能や認知能力の発達が遅れる可能性。
例: 言葉の遅れや学習の遅れが見られる。
(2) 肥満や生活習慣病のリスク
睡眠不足がホルモンバランスを乱し、過食や肥満の原因になることが。
成長期にこれが続くと、将来的な健康リスクが高まります。
(3) 精神的な問題
不安やうつ症状のリスクが増加する可能性が。
これは、十分な睡眠が取れないことでストレスが蓄積するため。
子どもの睡眠を守るために親ができること

子どもの睡眠のために親がしてあげられることとはどんなことでしょうか?
我が家では睡眠リズムを一定に保つ事を大切にしているので、幼稚園でのお昼寝も夜の睡眠に影響が出ないよう、寝かせすぎに注意してもらっています。
息子は寝始めると眠りが深く、ほおっておくと2.3時間眠り続け、夜眠れないということも起きるからです。せっかく眠っているのに起こすのはかわいそうな気もしますが、ここで眠らせて他の睡眠リズムが崩れてしまうリスクを考えると、ここでリズムを作ってあげることが重要と考えます。
科学的根拠に基づくポイント
以下は睡眠不足に関する科学的根拠。IQの発達に悪影響があるというのは恐ろしいですね。
今日から始められる!生活リズムを整えるための一歩
赤ちゃんや子どもにとって、睡眠は心と体を育む大切な時間。
でも「ちゃんと寝かせなきゃ!」と思うと、ついプレッシャーを感じてしまうこともありますよね。
大丈夫です!少しずつ始めていけば、必ず良い方向に進みます。
以下のポイントを参考に、今日から生活リズムを整える一歩を踏み出してみましょう!
1.いつものスケジュールに「ちょっとした変化」をプラス
- 寝る時間と起きる時間を一定に
最初は難しくても、同じ時間に寝かせるリズムを意識するだけで効果が出ます。
例: 「今日は30分早く布団に入ってみよう!」 - 寝る前の習慣を作る
お風呂の後に絵本を読む、静かな音楽を流すなど、毎日続けられる習慣を一つ決めてみてください。
2.明日が楽しみになる睡眠環境を整えよう
- 居心地の良い寝室作り
暗く静かで快適な温度に保つことがポイント。
お気に入りのぬいぐるみやブランケットを添えるのも◎。 - デジタルデバイスをお休みさせる
寝る1時間前からテレビやスマホは控え、少しずつ部屋を暗くすると、子どもの脳もリラックスしやすくなります。
3. 日中の活動がリズムを作る鍵
- 朝の光をたっぷり浴びる
起きたらカーテンを開けて、朝日を感じさせてあげましょう。
体内時計がリセット。 - 体を動かす遊びを取り入れる
公園遊びや体操など、日中の適度な運動が夜のぐっすり睡眠につながります。
4. 完璧を目指さない!小さな成功を喜ぼう
生活リズムはすぐに整うものではありません。
少しずつ改善しながら、できたことをお子さんと一緒に喜びましょう。
例: 「今日は昨日より10分早く寝れたね!」
5. 親子でリラックスする時間を大切に
親がリラックスしていると、子どもにもその安心感が伝わります。無理せず、家族みんなが心地よく過ごせるリズムを見つけていきましょう。
子どもの脳を育む魔法の時間 まとめ

「今日から少しずつで大丈夫」
たった一つの習慣を変えるだけでも、子どもの生活リズムは確実に良い方向に進みます。焦らず、親子で楽しみながら、少しずつ理想のリズムを作っていきましょう!
一緒に「ぐっすり寝てスッキリ起きる」明日を目指してみませんか?