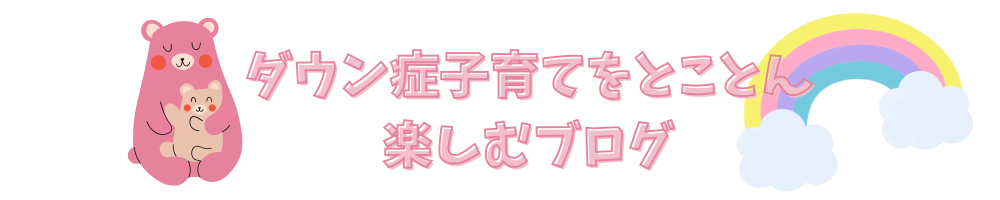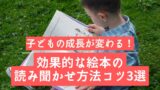こんにちは。ダウン症児の子育てをしている
ゆうママです。
今回は息子の難聴についてです。
息子は生まれてすぐの新生児聴覚検査で両耳リファー(Refer)という結果でした。
一般的に新生児聴覚検査では、
- 「パス(pass)」耳の聞こえに問題がない場合
- 「リファー(refer)」詳しい検査が必要な場合
と結果が伝えられます。
両耳リファーは両耳に難聴がある可能性を示唆しています。
その後、検査結果は「中度難聴」から「軽度難聴」、最終的に「正常」になりました。
難聴は治るのか?と思いますよね。
息子の場合は耳に異常があったのではなく、脳の発達と検査結果が連動していて、脳が発達することで、検査結果が良くなりました。これはあくまでも息子の場合ですが、どなたかの参考になれば幸いです。
右耳パス 希望の光

新生児期にはすべての赤ちゃんが病院で聴力検査を受けます。
その際の息子の検査の結果が「両耳リファー」。
最初の聴力検査はNICU(新生児集中治療室)で受け、その後、GCU(新生児回復室)に移動してから再検査。
2度目の検査結果は「右耳パス、左耳リファー」というもの。
「パス」が出た右耳でも、どこまで音が聞こえているのかは不明でしたが、少なくとも私の声が息子にに届く可能性があるという希望の光を感じました。
このころはまだ、息子の耳の穴が小さく難聴の原因は不明でした。
赤ちゃんの聴覚検査ASSR

赤ちゃんの聴覚を正確に調べるための検査に「ASSR検査」があります。
特に新生児や小さなお子さんに多く行われ、音刺激に対する脳の反応を測定することで、聴力の程度を判定。
赤ちゃんが眠っている間に行う検査で、安全かつ非侵襲的な方法です。
息子もこの検査を受け、聴力の状態を確認しました。
ASSR検査結果
左耳がほとんど聞こえていない「中度難聴」と診断。
中度難聴とは、ひそひそ話のような小さな音は聞こえず、補聴器の使用が必要になる可能性があるレベルの難聴。
診断を受けたとき、「やっぱり難聴なんだ…」というがっかりした気持ちは正直ありました。
ですが、担当の医師から次のような説明を受けました。
「この年齢の難聴は成長に伴って改善する場合があります。現時点で難聴の原因は特定できませんが、定期的に検査を続けていきましょう。」
難聴の原因が不明だった理由の一つは、息子の耳の穴が小さく、鼓膜が目視できなかったため。
ダウン症の赤ちゃんには耳の穴が狭いことがよくあり、その影響で耳垢がたまりやすいので、耳鼻科での定期的な掃除も必要でした。
音を届ける努力を続ける日々
それでも、「少しでも聞こえているなら」と、私たちは毎日話しかけを続けました。
医師からも「たくさんの音を聞かせてあげてください」とアドバイスされ、一番届けたい音は私たち夫婦の声だと感じたからです。
息子に話しかけたり、童謡を歌ったり、絵本を読み聞かせたりすることで、「音のある環境」を意識的に作りました。
不安や心配が尽きない日々でしたが、「聞こえないかもしれない」と諦めることはしませんでした。
聴力検査を続けた結果、改善が見られた息子の聴力
息子は定期的にASSR検査を受け続け、検査結果は少しずつ改善し、
生後8カ月の頃に受けた検査では「軽度難聴」と診断されました。
軽度難聴は、日常会話は問題なく聞き取れるものの、高音や低音が聞き取りにくい場合がある状態。
診断を受けたとき、「これなら日常生活で支障がない」と安心したのを今でも覚えています。
実際に一緒に生活をしている中で、息子が「聞こえが悪い」と感じることは全くありませんでした。
普通に話しかける声にも反応し、絵本の読み聞かせや歌にも楽しそうに反応。
ここまで聴力が改善すれば、親としても大きな安心感を得られます。
難聴がある子どもで親が一番心配する「発語」

難聴があると、親として一番心配になるのは「発語」。
耳の聞こえは言葉の発達にとって重要な要素であり、私たちも中度難聴と診断されたとき、補聴器の早期使用を検討。
しかし、息子の聴力が軽度難聴まで改善したため、まずは家庭でできることに注力することにしました。
話しかけるときに意識したこと
発語を促すために、私たち夫婦が話しかけの際に次の事を意識しました。
- ゆっくり、はっきり話す
子どもが聞き取りやすいスピードと発音。 - 口元をしっかり見せる
子どもが顔を見ているときは、口の動きを意識して見せる。
視覚的な情報は言葉を覚える助けに。 - 短い単語で話す
長く複雑な文章ではなく、簡単な単語を使い、わかりやすい表現に。 - 夫婦で単語を統一する
同じ単語を繰り返し使うことで、言葉の意味を理解しやすいことを意識。
これらの方法を毎日続け、1歳11か月には意味のある単語を話し始めました。
・にゃんにゃん
・ないないだー(いないいないばあ)
・パパ
・じいじ
・ばーちゃん
「ママ」がないのが悲しかったですが(笑)それでも話しかけの効果が見られ、ほっとしました。
ついに「正常」聴力検査終了
そして遂に2歳6か月での検査では結果が「正常」となりました。
耳を疑うような嬉しい結果。
その後の検査でも「正常」の数値が出たため、耳鼻科での聴力検査は卒業。
聴力検査は終わりましたが、耳の穴は小さいので耳掃除にはこれからも通います。
耳掃除の重要性と病院選びのポイント

息子は生まれた病院の耳鼻科に定期的に通っていました。
そこでお世話になった先生は非常に信頼できる方で、耳掃除の際も丁寧で、耳を傷つけたり出血させたりしたことは一度もありませんでした。
一方で、同じようにダウン症のお子さんを耳掃除に通わせているママたちから、次のような話を聞くことがありました。
- 「耳掃除で耳が血だらけになった」
- 「血が出すぎて別の病院を紹介された」
これらの話は、Instagramでも何度か目にしたことがありますし、知り合いのママからも直接聞いたことがあります。耳はとてもデリケートな部分ですし、大切なわが子が痛い思いをするのは避けたいものです。
病院選びは慎重に
耳掃除や治療において、安心して通える病院を見つけることはとても重要。
私は事前に病院の評判や先生の実績を調べることをおすすめします。
口コミサイトや、同じような経験をしているママたちの声を参考にするのも良い方法です。
「安心して任せられる先生に出会えること」
これは親にとっても子どもにとっても大きな安心感につながります。
難聴は治るのか
検査結果が「中度難聴」から「正常」に改善されたとき、私は正直「難聴が治ったんだ!」と思いました。
しかし、医師によると、今回のケースは「治った」のではなく、成長に伴う脳の発達によって聴力が改善されたものでした。
脳の発達と聴覚検査の関係
新生児期の聴覚検査は、赤ちゃんの脳がまだ発達途上であるため、正確な聴力が測れないことがあります。
そのため、特に発達に遅れが見られる場合、成長とともに検査結果が改善することがあるそう。
このようなケースでは、耳自体に問題がなくても脳が聴覚情報を処理しきれずに、聴覚検査で「リファー(詳しい検査が必要)」や「難聴」と判定されることがあります。
息子の場合も、脳の発達が聴覚機能の改善に大きく寄与していたようです。
あきらめずに希望を持っていて良かったと思えた今日

もし新生児期の検査で「難聴」の結果が出たとしても、「どうせ聞こえない」と話しかけや音の刺激をあきらめるのは、もしかすると早すぎるのかもしれません。
今回の経験を通じて私は、声かけや音の刺激が脳の発達に良い影響を与える可能性があることを実感しました。
ただし、すべてのケースに当てはまるわけではないことも事実。
それでも、親として子どもにたくさん話しかけ、音を届ける努力を続けることは、きっと無駄にはならないと思います。
この経験が、同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。