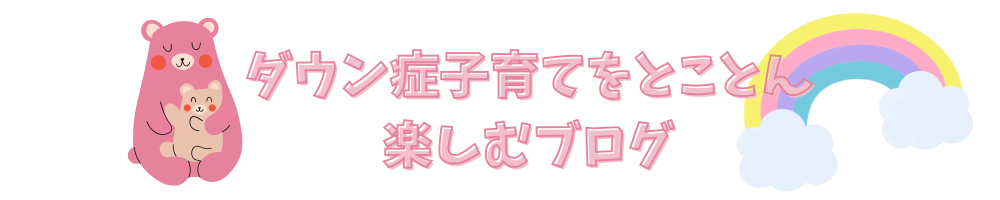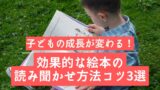こんにちは。ゆうママです。
本日も『脳育』コツコツ頑張ります。
最近、息子の子育ての中でこんな悩みに直面しました。
・叱っても、言い聞かせても効果がない
・注意すればするほど、問題行動がエスカレート
実は、ダウン症児の特性を理解するだけで、こうした悩みがあっさり解決するケースもあります。
ダウン症児には、相手の反応を楽しむあまり問題行動を繰り返す特性が見られることがあります。
そのため、
「強く叱れば止まるはず」
「根気よく言い聞かせれば解決するはず」
と思い頑張ることが、逆に行動を助長させてしまう場合も。
そこで試してほしいのが、特性に基づいた「反応しない」対応。
問題行動へのアプローチを変えるだけで、驚くほどスムーズに改善することがあります。
この記事では、その具体的な方法について詳しく解説します!
ダウン症児によくある問題行動
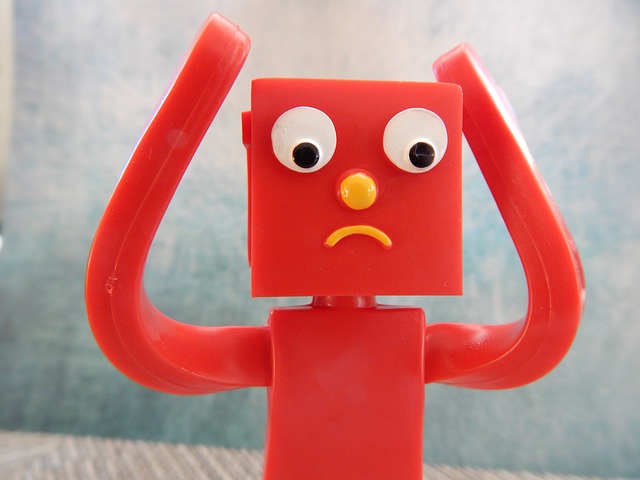
ダウン症児の子育てでは、以下のような問題行動に悩まされる話をよく耳にします。
我が子も一時期、人の顔を叩くことがあり、とても困りました。
痛みを伴う行動に、親としては当然叱り、言い聞かせようとしますよね。
「ダメだよ。痛いよ。ママはとっても悲しいよ」
しかし、こうやって注意しても、叩く回数はむしろ増える一方。
そこで、さらに強く叱ってしまうこともありました。
ところが、我が子は叱られるとニコッと笑い、むしろ嬉しそうな表情を見せるのです。
時には、叱られて泣くこともありますが、泣き止んだと思ったら何事もなかったかのように遊び始め、また同じ行動を繰り返すことも。
親としては本当に悩ましい状況ですが、問題行動の理由とダウン症児の特性を知ることで、この困りごとの答えが見つかるかもしれません。
【問題行動の理由を知る】まずは原因を見極めよう

お子さんが問題行動を起こしたとき、その理由を考えたことはありますか?
以下の2つのケースのどちらに当てはまるかを確認してみましょう。
A:ストレスや不満を感じているが、言葉で伝えられず問題行動を起こしている
- 何か困っていることや不安がある
- 自分の要求が伝わらずイライラしている
Aの場合は理由を取り除く必要があります。
特性を考える前に子どもが抱えている問題に目を向け、強くしかるより、できる限りその問題を理解してあげなければいけません。
子どもを観察し、不満な点を見つけ話し合い、改善されたこともありました。
時間はかかりますが何度も言い聞かせて本人が納得するのを待つ。
ダウン症児は頑固な事が大いにあるので、親も根気と粘り強さが必要に。
B:理由が分からない。特に機嫌が悪いわけでもないのに、日常生活の中で突然始まる
- 特定の原因が思い当たらない
- 親の反応を楽しんでいる可能性が高い
以下の記事では、Bのケースについて、その理由と効果的な対処法を解説していきます。
Bの場合:なぜ問題行動がエスカレートするのか?
お子さんが親御さんの反応を楽しんでいる可能性があります。
例えば、叱るたびに大きな声を出したり、真剣に注意する様子を見て「いつもと違う大人の反応」に興味を持ち、面白がってしまうことが。
その結果、「叱られても楽しい!」と感じてしまい、問題行動を繰り返してしまうのです。
私が専門医から学んで効果のあった具体的な対処法についてお話しします。
【反応を楽しむ問題行動に「反応しない」が効果的?】試したい3つの対処法

お子さんが問題行動を起こし、それを楽しんでいるように見えると、親としては余計に腹が立ち、「痛い」「不快だ」ということをわかってもらいたくなります。
しかし、こういった場合の効果的な対処法は以下の3つです。
① 問題行動を完全に無視する(反応しない)
これは専門医や児童発達支援の先生からも「最も有効な方法」とすすめられた対応策。
- リアクションを一切しないことで、子どもが「面白い」と感じる要素を取り除く
- 表情、声のトーン、動きなど、すべて無反応を貫く
「無視する」と聞くと、可哀想な気持ちになりますが、無視というよりは「動じない」の方が正しい言い方かもしれません。
親にとって精神的に辛い場面もありますが、根気強く続けることで効果が現れます。
② その場から離れて1人にする
一緒に食事をしているときや遊んでいるときに問題行動があった場合、無言でその場を離れるのが効果的。
- 背中を向けてその場を離れ「自分の行動のせいで、大好きな人がいなくなった」と気づかせる
- 行動の因果関係を学ぶきっかけを与える
③ 好きなものを禁止する
子どもの好きなものを活用して、行動の結果を意識させる。
- おやつ、好きな食べ物、動画視聴(例:YouTube)などを一定時間禁止
- 「叩いたから今日は○○はお預けだよ」と伝え、行動と結果を関連付けて理解させる
注意点
これらの方法は一度試しただけでは効果が出にくい場合があります。
大切なのは、一貫性を持って対応を続けること。
親が迷ったり、対応を変えたりすると子どもは混乱してしまうため、まずは取り組む方法を一つに絞り、実践してみてください。
【ダウン症児の特性を理解しよう】叱るより「反応しない」が効果的な理由

問題行動に対して無視したり、好きなものを取り上げるのは、親として心が痛むことも。
「叱ったり、言い聞かせたりして教える方が良いのでは?」と感じる方も多いでしょう。
それでも「反応しない」対応が効果的とされるのは、ダウン症児の特性が関係しています。
ダウン症児がどのように物事を受け取り、なぜ叱ることが逆効果になるのか、その理由を詳しく解説していきます。
ダウン症児の特性
ダウン症児には、以下のような特性が見られることがあります。
言い聞かせが難しい現実と親の葛藤
「悲しさや苦しさを言い聞かせても心に届きにくい」というのは、親としては少しショックですよね。私も最初は、
「うちの子は優しい子だから、きっと理解してくれる」
「根気よく言い聞かせれば伝わるはず」
そう思っていました。
しかし、何度伝えても同じ問題行動を繰り返されると、親としても心が疲弊してしまいます。
さらに、叱ったときに泣いていた我が子が、あっさり泣き止んで遊び始める姿を見て「どうして通じ合えないのだろう?」と悩むこともありました。
「特性だから」と割り切る選択肢
私個人の見解ですが、時には「特性なんだから、言い聞かせるのはやめよう」
と思い切って対応を変えてみることも大切。
この決断が、親にとっての心のモヤモヤを解消し、無駄に感じるやり取りを減らしてくれます。
実際に、我が家では「反応しない・動じない」対応を始めてから1週間もしないうちに、問題行動が完全に止まりました。
【ダウン症児の問題行動対処法まとめ】親ができる効果的な対応

お子さんが問題行動を起こしたとき、次の手順で対処を試してみてください。
個性を大切に、柔軟に対応を
「ダウン症児」と一括りにされがちですが、お子さん一人ひとりにもちろん個性があります。
この方法が必ず全てのお子さんに当てはまるわけではありませんが、我が家では驚くほど簡単に問題行動が解決しましたので、シェアさせていただきました。
「試してみよう」と思えるものから、ぜひ取り入れてみてください。
お子さんとの新たな向き合い方が、解決への一歩になるかもしれません!