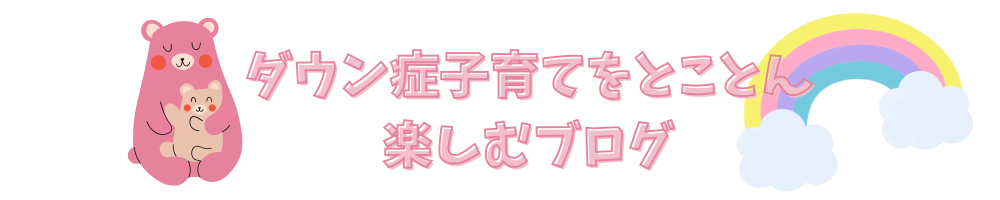こんにちは。ゆうママです。
本日も『脳育』頑張ります!
「モンテッソーリ教育」という言葉を、ダウン症児の子育てをしているとよく耳にしませんか?
そもそもどのような教育なのか気になるところですが、
「モンテッソーリ教育はダウン症児に向いている」
といった声を聞くこともあります。そうなると、ますます気になりますよね。
そこで今回は、モンテッソーリ教育について私が調べたこと、そしてなぜダウン症児に向いていると言われているのかをまとめました。
興味のある方はぜひ読んでいただき、育児の参考にしてみてください。
ちなみに、我が家では「モンテッソーリ教育を取り入れない」という決断をしました。
息子の性格には向いていると思いましたが、モンテッソーリ教育を取り入れている施設が近くになかったことと、現在の目標が「協調性」「集団行動で苦手にも向き合う」「ルールを守ること」だからです。
ただ、今後考えが変わる可能性もあるため、知識として知っておくことは大切だと思っています。
気になっている方の参考になれば嬉しいです。
モンテッソーリ教育とは?
モンテッソーリ教育は、もともと 発達障害児のための教育法 として考案。
1907年、マリア・モンテッソーリはイタリアのスラム街にある「子どもの家(カサ・デイ・バンビーニ)」で、知的障害のある子どもたちに独自の教育法を実践。
その結果、彼らが知的に大きく成長し、通常の子どもと同じ水準の試験をパスするようになったのです。
その後、この教育法は健常児にも効果があることがわかり、世界中に広がりました。
現在では、発達障害児やダウン症児の支援だけでなく、一般の幼児教育にも広く採用されています。
モンテッソーリ教育の特徴

モンテッソーリ教育には、以下のような特徴があります。
このような特徴により、モンテッソーリ教育は自立心や責任感、他者への思いやりを育むことを目的としています。
モンテッソーリ教育がダウン症児に適していると言われる理由
モンテッソーリ教育の理念や方法が、ダウン症児の発達支援に適しているとされる理由はなんでしょうか。
モンテッソーリ教育は、そもそも発達障害児の支援から発展した教育法であるため、ダウン症児の潜在能力を引き出す柔軟なアプローチを持っていると言われているんですね。
ここまで読むと、好きな事にはとことん集中する息子にはとても良い!との気持ちになりますが、デメリットはどうでしょうか?
モンテッソーリ教育の課題と批判
モンテッソーリ教育には多くの利点がありますが、以下のような課題も指摘されています。
- 協調性の育成に関する懸念
自主性を重視するため、集団行動や協調性が育ちにくいとの指摘があります。
ただし、「縦割りクラス」では自然と助け合う機会があり、社会性を養う工夫もされています。 - 公立学校への適応の難しさ
モンテッソーリ教育では自由に学ぶスタイルを採用しているため、時間やカリキュラムが厳格に管理される公立学校に適応しにくい場合があります。 - 教育者の質のばらつき
モンテッソーリ教育を名乗る施設でも、適切な認定を受けていない場合があり、教育の質にばらつきがあります。 - デジタル教育への対応不足
IT機器を使用しない方針を取ることが多いため、デジタル教育が進む現代社会に合わないと感じる人もいます。 - 費用と家庭の負担
教具や環境整備にコストがかかるため、家庭の負担が大きくなることがあります。
また、親の理解と協力も求められます。
協調性に関しての補足
モンテッソーリ教育は「協調性が育たない」と言われることがありますが、適切な環境を整えることで補えるとも言われています。
- 自主性と協調性のバランス
子どもが自分のペースで活動するため、協力する機会が少ないと感じる場合があります。
しかし、異年齢の子どもが学ぶ「縦割りクラス」では、自然と助け合いの精神が育まれます。 - 集団行動の経験不足
大人数で統制された活動が少ないため、一般的な学校環境に移行する際に戸惑うことがあります。これを補うためには、外部での集団活動や共同作業の機会を提供することが有効です。 - 社会性を自然に育む仕組み
モンテッソーリ教育では、強制的な同調ではなく、子どものペースで社会性や協調性を発達させることを目指しています。そのため、適切な環境を整えれば、協調性も育つ可能性があります。
モンテッソーリ教育における「褒める」の考え方

私がモンテッソーリ教育に関して調べていた時に「褒めない」との記述を目にして、それでは絶対我が家には合わないと感じましたが、きちんと調べてみると「褒め方」に特徴があるようです。
この褒め方は私が子どもの褒め方に関して勉強していた際に、子どもにただ、「すごい!」「天才!」などというより、そこにたどり着くまでの「過程」を褒めることがとても効果的だと他でも耳にしたことがあるので、実際に自分が今子育てをしていて取り入れるように心掛けている事です。
満点の結果でなくても、20%ほどの出来であっても、そこまで努力したことを褒めるようにしています。
モンテッソーリ教育とシュタイナー教育の違い
モンテッソーリ教育と並んで有名な教育法に シュタイナー教育 があります。違いを比較してみました。
| モンテッソーリ教育 | シュタイナー教育 | |
| 目的 | 自立した個人を育てる | 想像力と芸術性を重視 |
| 教育の中心 | 科学的・論理的な遊び | 芸術や感性を重視 |
| 教具 | 視覚・聴覚を使った感覚教具 | 木製の素朴なおもちゃ |
| 教師の役割 | 子どもを観察し環境を整える | 子どもを導く芸術的な存在 |
モンテッソーリ教育は 「自由」ではなく「自立」を目指す という点が特徴です。
一方で、シュタイナー教育は 創造性や直感を育てる ことに重点を置いています。
モンテッソーリ教育を取り入れた有名人
モンテッソーリ教育を受けたことで知られる有名人には、以下のような人物がいます。
- ジェフ・ベゾス(Amazon創業者)
- ラリー・ペイジ & セルゲイ・ブリン(Google創業者)
- マーク・ザッカーバーグ(Facebook創業者)
- バラク・オバマ(元アメリカ大統領)
- アンネ・フランク(『アンネの日記』著者)
彼らはみな、幼少期にモンテッソーリ教育を受けたことで、自主性や創造性を伸ばしたと言われています。
モンテッソーリ教育とダウン症育児の相性
モンテッソーリ教育は、ダウン症児の発達を支援する上で有効な教育法の一つ。
自発性を尊重し、感覚教具を活用した学びを提供することで、彼らの可能性を引き出しやすくなります。
一方で、集団行動の経験が不足しがちであるため、公立学校への移行を考える場合は、補完的な集団活動を取り入れることが望ましいでしょう。
また、教育の質にばらつきがあるため、施設選びには注意が必要です。
モンテッソーリ教育は、ダウン症児の特性に寄り添いながら、自立心や社会性を育む可能性を持つ教育法です。子どもの個性や成長に合った環境を整えることで、そのメリットを最大限に活かすことができるでしょう。
一般的な「褒める」行為をあまりしません。
これは、「子どもが自らの成長や学びに対して満足感を持つこと」を大切にしているからです。
最後に

【モンテッソーリ教育を取り入れなかった理由】
- 近くに施設がない
- 成長と共に協調性を重視した
- 苦手な事、合わないと感じていることにも向き合って欲しいとの親の方針
我が家では、好きなことをとことんやらせる教育方針だった事と、本人が好きな事をとことん追求する性格だったために、一時期はモンテッソーリ教育が向いているかもしれないと考えたこともありました。
実際、息子の通っている幼稚園はモンテッソーリ教育ではありませんが、本人の自主性を尊重し、自由に好きなことをやらせる校風です。
この環境のおかげで、のびのびと楽しく過ごせていますが、わが子の場合は甘えが出てしまい、やりたいことしかやらず、協調性が育ちにくいと感じるようになりました。
そこで、習い事や家庭では、集団行動やルールを守ることを意識したサポートを取り入れています。
モンテッソーリ教育を取り入れるかどうかは、それぞれの家庭の教育方針やお子さんの性格によって異なります。この記事を読んで「我が家には合いそう」と感じた方や、「子どもに合っていそう」と思った方は、積極的に取り入れることで、お子さんの力を伸ばす助けになるかもしれません。
また、すべてをモンテッソーリ教育にする必要はなく、本屋さんにはモンテッソーリ教育を取り入れた育児本が多く並んでいますし、モンテッソーリ教育を意識したおもちゃも数多く販売されています。
我が家にもいくつか取り入れています。
大切なのは、お子さんと親御さんに合ったものを選び、無理のない範囲で取り入れること。
必要な部分だけ活用するのも、良い方法ではないでしょうか。